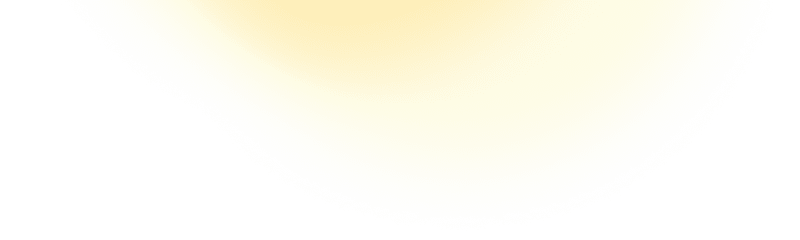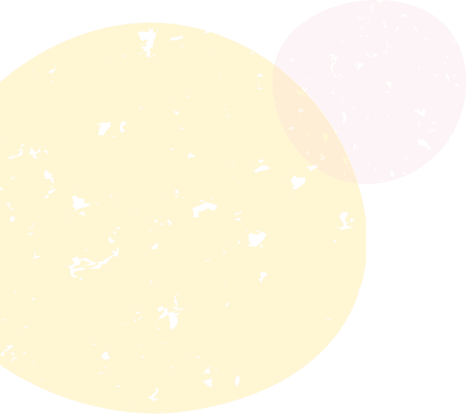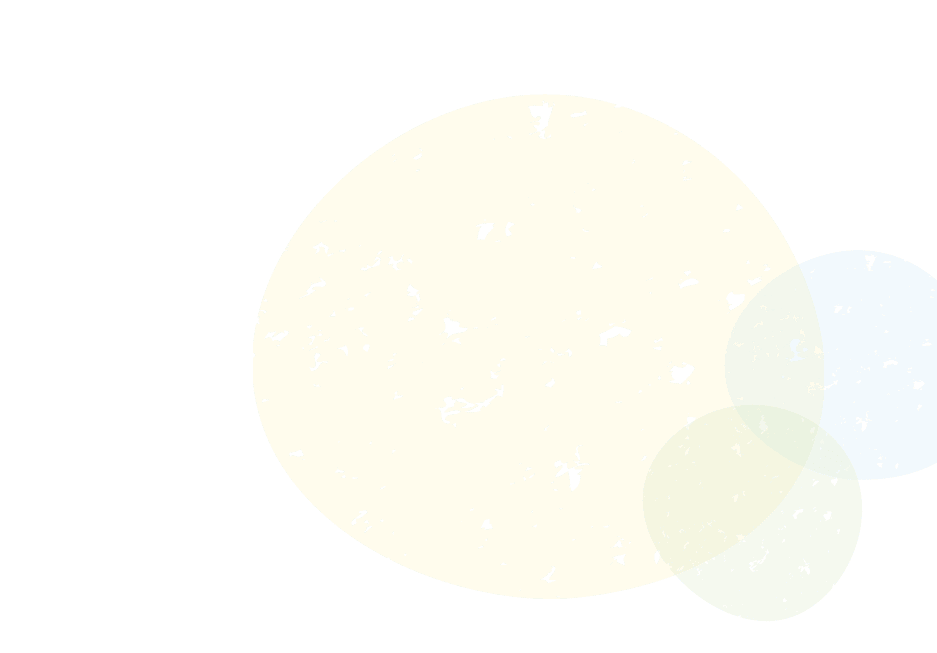業務特化型サービスが自治体のDX推進に最適な理由

カスタマイズ可能でどんな業務にも適応できる多機能なサービスは一見理想的に見えますが、業務特化型サービスには異なる多くの利点があります。
このコラムでは、自治体職員や周辺関係者が抱える課題に対して、なぜ業務特化型サービスがDX推進に最適なのかを詳しく説明します。
多機能型サービスと業務特化型サービスの違い
まず、多機能型サービスの魅力について考えてみましょう。多機能型サービスは、設定などのカスタマイズで画面や機能を柔軟に作りこめるため、1つのサービスで多様なニーズに応えることができます。しかし、これにはいくつかの課題も伴います。例えば、以下のような点が挙げられます。
- 初期導入時の要件整理:
職員様のニーズについて、解決方法を検討し、解決手段を多機能サービスでどのように実現するか事前に整理してからカスタマイズするため、導入時に多くのリソースを必要とし、改善に時間を要します。 - 複雑さの増大:
多機能であるがゆえに、職員様が使いこなすためには高い学習コストがかかります。 - 維持メンテナンスによる職員負担:
多様な機能があるため、バグや不具合の発生リスクも高まり、維持メンテナンスの負担があり、効率化のための施策なのにかえって業務負担が増えることがあります。
一方、業務特化型サービスは特定のニーズに特化しているため、以下のような利点があります。
- 初期導入速度:
改善対象を特定の業務に絞ることで、導入までの検討範囲が限定的であり、最適なサービスを選択することで素早い改善が可能です。 - 使いやすさ:
特定の業務に特化しているため、ユーザーが使いやすく、学習コストが低いです。 - 高いパフォーマンス:
特定の業務に特化することで、その業務において高いパフォーマンス、改善効果を発揮します。
業務特化型サービス導入における成功事例
例えば、ある自治体では介護認定業務の認定調査事務の改善を検討していました。当初は汎用的なOfficeExcelや多機能サービスであるクラウドサービスを使った調査事務の電子化を検討されていましたが、セキュリティの担保や業務フローの変更、利用媒体の調整などニーズに合わせた要件整理に非常に時間がかかっており、改善に向けた検討に非常に多くのリソースがかかっておりました。
現場のご担当者からご相談いただき、介護認定支援サービス「ねすりあ」と認定調査結果のAI診断サービス「Aitice」を組み合わせた改善後の業務フローをご提案し、影響範囲などに絞って検討いただいた結果、ご提案から業務改善まで調達を含めて4か月という短いスパンで改善を実感いただけることができました。
自治体職員様との共創の重要性
成功事例として挙げた介護認定支援サービス「ねすりあ」をはじめ、他のサービスもすべて自治体の現場担当者様の強い思いに共感し、「共創」の活動によって生み出されたものです。良い特化型サービスを開発するためには、自治体職員の現場での経験や知識をヒアリングし、業務全体の課題について深く理解することで、実際のニーズに即したサービスを作ることができます。
私たちは、一つの自治体だけでなく、複数の自治体様と協力し、インタビューや実証実験を通じて、業務特有の共通課題を特化型サービスで解決するよう努めています。
職員の方や市民の方と一緒になってサービスを開発することで、自治体職員も市民も満足するサービスが生まれます。
相談してみよう!業務特化型サービスの可能性
何か困ったことがあれば、ぜひ一度ご相談ください。私たちは共に課題を解決し、より良い未来を創るためのパートナーです。「じちえる」では自治体職員や協業先が抱える具体的な課題をしっかりと把握し、その課題に対する最適な業務特化型サービスを共創により生み出してきた実績があります。コラムをご覧いただいているあなたの課題も一緒に解決できるかもしれません。是非、このコラムを参考にして、業務特化型サービスの開発に一緒に挑戦しましょう。
まとめ
自治体職員、市民の皆さんにとって、業務特化型サービスの導入は自治体の限られた予算やリソースを有効に活用し、日常業務の効率化や市民サービスの向上に大きく貢献します。また、協業先にとっても顧客のニーズに的確に応えられる競争力を持つことができます。
今回のコラムでは自治体DXの先、自治体職員や市民の皆様にとってよりよい生活を目指すためには業務特化型サービスの活用が最適であることをご紹介しました。また次回のコラムも楽しみにしていただければ幸いです。