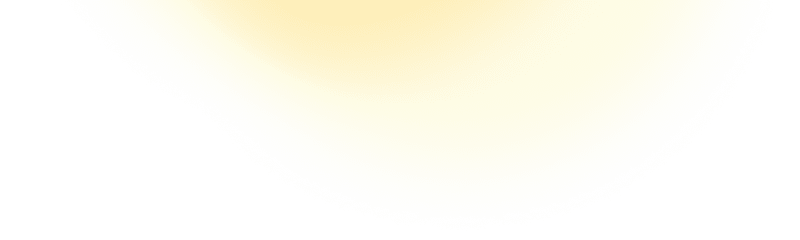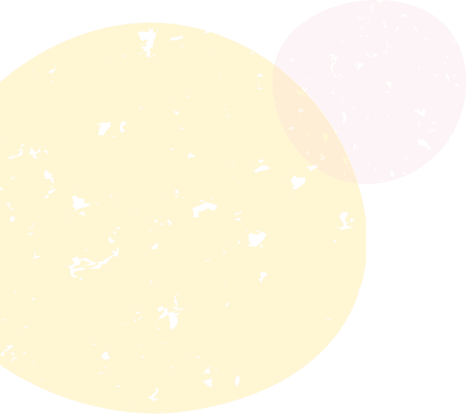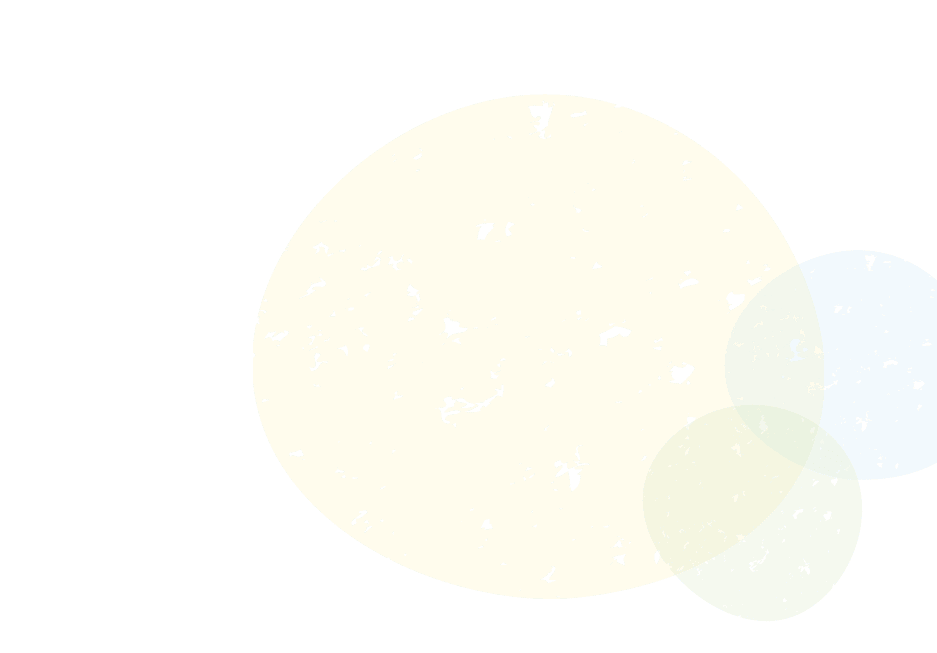生成AIによる自治体業務効率化の可能性

毎日いたるところで目にするキーワード『生成AI』。
どのようなシーンで利用できるのか、どんなことに気を付けるべきなのか。
自治体で働く方に見て欲しい『生成AI』の取説です。
最近流行りの生成AIって?
テキスト、画像などのコンテンツを生成するAIモデルを「生成AI」と呼びます。近年では、OpenAI社のChatGPTを皮切りに、GoogleのGeminiなど、人間のように文章を生成することができる高度なモデルが次々とリリースされています。これらのモデルは、単なる検索や分類だけでなく、新しいコンテンツを生み出すことができる点で革新的です。
従来のAIとの違いについて
従来のAIモデルと最も大きく異なる点は、汎用的に様々なタスクに対応できる点です。従来のモデルでは、分類や予測など、学習済みの特定タスクに対して有効な結果を出力することができましたが、学習範囲外のタスクには対応できないという課題がありました。
一方、近年の大規模言語モデル(LLM)を活用した生成AIは、自然言語処理を基盤とし、より柔軟な対応が可能になっています。
例えば、自治体業務においては、
- 文書作成や要約の自動化
- 職員の問い合わせ対応の補助
- 過去の議事録や法令をもとにしたレポート生成
想定されるユースケースについて
自治体業務の効率化において、生成AIは以下のようなシーンで有効に活用できます。
(1) 文書作成の効率化
自治体では多くの文書作成業務が発生します。例えば、会議の議事録、報告書、広報資料などです。生成AIを活用することで、テンプレートを基にした文書の自動生成や、文書の要約・校正が可能になり、職員の負担を大幅に削減できます。
(2) 住民からの問い合わせ対応
生成AIを活用したチャットボットを導入することで、住民からの問い合わせ対応を自動化できます。特に、よくある質問(FAQ)への対応や、行政手続きの案内などに適用することで、職員の業務負担を軽減し、住民サービスの向上にもつながります。
(3) 行政データの分析と報告書作成
自治体が持つ膨大なデータ(人口動態、財政データ、防災情報など)を解析し、分かりやすい形でレポートを作成する作業も、生成AIによって効率化できます。例えば、議会向けの説明資料や施策の効果分析レポートの作成を自動化することで、業務のスピードを向上させることが可能です。
(4) 法令・政策の要約と解説
自治体職員が新しい法律や政策を理解し、適切に業務へ反映するには時間がかかります。生成AIを活用すれば、法令文の要約や、特定の業務への影響を解説するドキュメントを自動生成することができ、迅速な対応が可能になります。
利用におけるリスク等について
生成AIの導入には大きなメリットがある一方で、いくつかのリスクも考慮する必要があります。
(1) 情報の正確性の問題
生成AIは高度な文章生成能力を持っていますが、必ずしも正しい情報を出力するとは限りません。誤った情報が住民対応や行政文書に使用されると、混乱や問題が発生する可能性があります。そのため、重要な業務に活用する場合は、必ず職員が内容を確認するプロセスを設ける必要があります。
(2) セキュリティとプライバシー
自治体業務には個人情報や機密情報が含まれるケースが多いため、生成AIを利用する際には適切なデータ管理が求められます。特に、クラウド型のAIサービスを利用する際には、データの取り扱いポリシーを十分に確認し、必要に応じてオンプレミスでの運用を検討することが重要です。
(3) AIの倫理的課題
AIのバイアスや透明性の問題も考慮する必要があります。例えば、特定の住民層に対する不公平な対応が発生しないよう、AIの出力内容を適宜チェックする体制を整えることが求められます。
(4) 過度な依存によるスキル低下
生成AIが広く活用されることで、職員のスキル低下につながる可能性も指摘されています。適切な業務範囲を定め、人間とAIが補完し合う形で運用することが重要です。
まとめ
生成AIは自治体業務の効率化に大きく貢献する可能性を秘めています。文書作成の支援、住民対応の自動化、データ分析の迅速化など、多くの分野で導入の余地があります。しかし、その一方で、情報の正確性、セキュリティ、倫理的な課題など、慎重な対応が求められる点も少なくありません。
自治体においては、生成AIの特性を正しく理解し、適切なガイドラインを策定した上で導入を進めることが望まれます。AIを活用しながらも、人間の判断や確認プロセスを適切に組み合わせることで、より効果的な自治体業務のデジタル化が実現できるでしょう。